この度は千松信也さんの「ぼくは猟師になった」という作品を読みました。ワナ猟の方法や工夫、獲物の解体方法やレシピ、獲物と初めて対峙し命を奪ったときに感じたことなど現役猟師の等身大の記録が描かれています。私自身食べることが好きでジビエを食べることもあるので食べ手として猟の背景など理解したいと思い読み始めました。そしたらビックリ、ここ最近読んだ本で一番面白かったです!
著者が初めてシカを捕まえた時の状況を書いている文章がめちゃくちゃ好きでした。シカと著者の息づかいが聞こえてきそうな臨場感、初めての獲物への喜び、一方で苦労や奮闘、そして一匹の野生動物の命を奪うことに対する葛藤や罪悪感などの複雑な感情まで丁寧に描かれています。その場に居合わせていると錯覚するような臨場感に息をのみましたし、空気感に非常に引き込まれました。猟師初心者の著者が初めて獲物を獲った時の感動がヒシヒシと伝わってきて胸が熱くなりました。この文章をはじめ、本作を読んでいる最中に「うわぁ、猟師いいなぁ」と心の中で何度つぶやいたことか。こんなに猟師の魅力を伝えている本はあるのだろうかと感じるくらい良くて、猟について全く知識がない方でも楽しむことができる内容になっていますし、猟師になりたいと思っている人はその思いを後押ししてくれる一冊になると思います。
また、狩猟以外の野生動物の調理法や獲った獲物の皮のなめし方など猟師の生活について書かれてる点が個人的には一番面白くて読む価値があると思っています。著者が勉強したりどうしたら美味しく無駄なく肉を頂けるか、より良くなるか試行錯誤してたどり着いて生きた情報が満載過ぎて魅力的過ぎました。文章だけでなく、イラストや写真も(前述したシカを捕まえた時の写真や解体作業の写真もあります)多用されており、わかりやすいです。多くの人は実行しないであろう薪風呂の作り方(写真付きで笑)まで書かれていて面白さ爆発してました。著者である千松信也さんのトガリ具合が大好きです。独自性が高く情報の質、量という点でも非常に価値のある一冊だと断言できます。
ここから、引用など用いて皆さんをワナ猟の世界、猟師さんの世界、本作の魅力を少しだけ紹介させていただければと思います。気になった方は本作を買ってこの世界にどっぷり浸かっちゃってください。
それでは本作の魅力を紹介させていただきます。
~作品情報~
題名:「ぼくは猟師になった」
著者:千松信也
出版:新潮社
ページ数:244ページ
目次
- :自然と向き合う中で感じたこと、ワナ猟の方法や工夫、獲物の解体方法、調理法、皮のなめし方まで生きた感情、情報満載!猟師っていいなと何度も思わせてくれる現役猟師等身大の記録
- 私が読んだ動機
- こんな人にオススメ
- 作品説明
- 初めて獲れた鹿に大興奮!著者の喜びや感動、罪悪感など複雑な感情が伝わる文章にワクワクが止まらない!
- 狩猟の世界にどっぷり浸かろう!想像以上に奥が深いワナ猟の世界をイラストや図解も交えて超わかりやすく解説、ワナ猟のバイブル的な本になるかも!
- 猟だけじゃない!現役猟師の生き方から楽しさが伝わってくる。普段の生活で触れる事のない生きた情報、未知の世界に心が躍る!
- まとめ
1.自然と向き合う中で感じたこと、ワナ猟の方法や工夫、獲物の解体方法、調理法、皮のなめし方まで生きた感情、情報満載!猟師っていいなと何度も思わせてくれる現役猟師等身大の記録
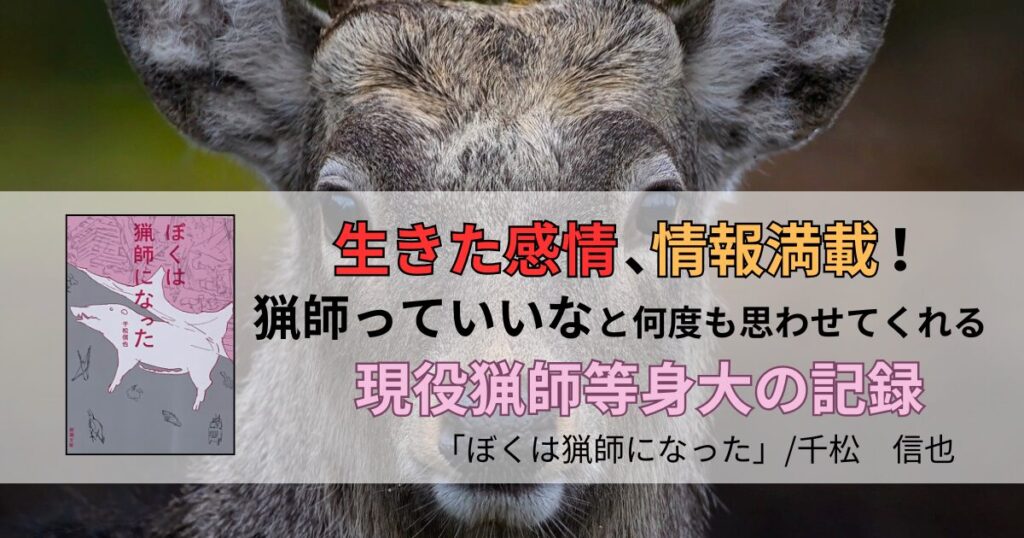
私が読んだ動機
- 食べることが好きで、野生鳥獣の狩猟法や習性など詳しくなりたいと思ったから
- 猟師というと鉄砲のイメージがあったが本作の著者はワナ猟を専門としており、獲物の狩猟方法や生き物との向き合い方など興味があったから
- 猟師になるためにはどうしたらよいのか、猟師の人たちがどんな風に過ごしているのか気になったから
こんな人にオススメ
- 猟師になりたいと思っている人
- ワナ猟に興味がある人
- ワナ猟を始めたいと思っている人
- ジビエや狩猟方法について詳しくなりたい人
- ジビエを食べることが好きな人
- 自然が好きな人
- 猟師の生活に興味がある人
作品説明
著者は京都大学在籍中に狩猟免許を取得し、先輩猟師から伝統のワナ猟、網猟を学ぶ33歳現役猟師。具体的な動物の捕獲方法や処理の仕方、解体、精肉の仕方、料理のレシピだけでなく著者がどういったきっかけで狩猟をしたいと思い、実際に猟師になったのか、獲物の命を奪った時、食べた時の状況や感じたことなど考えや生活の一端まで描いた現代の猟師の等身大の記録。
初めて獲れた鹿に大興奮!著者の喜びや感動、罪悪感など複雑な感情が伝わる文章にワクワクが止まらない!

本作は著者が幼少期の頃の記憶からはじまり、ワナ猟を始めるきっかけなどが最初に書かれています。そして猟師となりついに初めての猟期を迎えるわけですが、そこで初めてワナにかかった鹿を発見し、命を絶つために格闘します。その時の文章が著者の感情が溢れていて非常に引き込まれました。引用させていただき紹介したいと思います。
飼育小屋のにおいがして……初めての獲物
その瞬間、頭の中が真っ白になりました。
僕の目の前には大きなメスジカがこちらを向いて立っているのです。前脚に僕のしかけたククリワナをぶらさげています。興奮して鼓動が激しくなるのを感じながら、じわじわとうれしさがこみ上げてきました。
「よっしゃ、シカ獲れたー!」
その日もいつものようにワナをしかけたポイントヘバイクで見回りに出発しました。〔中略〕猟期が始まってすでに二週間。毎日見回りに行くも、十丁ほどしかけたワナには何もかからず、その日もあまり期待していませんでした。まわりの猟師からも「一年目からそうそう簡単には獲れるもんやないで」と言われていたし、自分がしかけたワナのポイントや架設の仕方に問題がないのかどうかすらわからず、暗中模索の状態でした。
山に入ったら、けもの道をつたいながら順々にワナを確認していきます。五つ目までは何の変化もなし。六つ目の、少し離れたワナの確認に向かいました。その時、なんだか妙なにおいを感じたのです。
なんだこれ、動物園の飼育小屋のにおいのような……。あ……、ひょっとしてっ!
一気に慎重になります。ゆっくりとワナを確認しに行くと、現場は以前とちょっと雰囲気が違います。生えている笹は不自然に折れ曲がり、地面にも掘り返されたような跡があります。そして肝心のワナは見あたりません。どうなってるんだろうと怪訝に思い、もう数歩近づいた瞬間、ガサガサガサッ!と藪が揺れ、その向こうにいるシカを発見したのです。
シカとの格闘
その後、人生初の獲物に対する興奮をなんとか鎮め、必死で師匠の角出さんから教わった処理の仕方を思い出しました。
「〔前略〕おまえは鉄砲を持っとらへんから、トドメを刺すには近くにある手頃な固い木をノコギリで切って、それでどついて動かんようにするんやで。シカなら後頭部、イノシシやったら眉間やからな。その前にロープで、ワナにかかったのとは別の脚をくくって動けんようにするんが確実やな」
僕はとりあえず、その場を離れ、手頃な木を切りロープを準備しました。しかし、いざシカの脚をロープでしばろうとするとなかなかうまくいきません。シカでも油断すると蹴られて骨折する場合があると聞いていたので、遠くから恐る恐るの作業になってしまい、うまくいかなかったのです。いつまでたってもロープはかからずだんだん焦ってきます。
もう脚はやめて首にかけよう。そう思い、首めがけて輪にしたロープを投げました。しかし、何度繰り返してもうまくいきません。途方に暮れましたが、どうすることもできず、ただロープを投げつづけました。何度目かのロープがまた首にかからず地面に落ちたその時、ロープを嫌がったシカが逃げようと動き、近くの木にワナのワイヤーを絡ませてしまったのです。シカは動けなくなり、しゃがみ込んでしまいました。
これはラッキーやな。もう、多少危険でもやるしかないわ。
僕は覚悟を決め、木の棒を振りかざしてシカに近づき、渾身の力を込めてシカの後頭部をどつきました。一発でした。シカはその場に倒れこみ、しばらく痙攣。その後、わずかに鳴き声を漏らしたあと、動かなくなりました。
さすがにいろんな感情が湧き上がってきます。〔中略〕これだけ大きな野生動物を自ら捕獲し、その命を絶つというのは初めての経験です。そして、正直、子供の頃に観たアニメや奈良公園への遠足などですり込まれた”シカはかわいい動物”というイメージも頭の中にあります。罪悪感のようなものも湧いてきました。
でも、これは食べるための狩猟であり、罪悪感を感じるほうがシカに対して失礼なんじゃないのか。
そうは言っても、こんなことをしなくても食べ物は充分あるじゃないか。
どんどん混乱していきます。
シカはまだ死んだわけではなく、脳しんとうのような状態で、心臓は動いています。
僕はとりあえず、すべての感情を押し殺し、教わった手順で処理をはじめました。
千松信也「ぼくは猟師になった」新潮社、49,50,51,53頁
シカを発見したときの状況、シカを気絶させるまでの格闘の様子がまじまじと頭の中に映し出されました。そして、とどめを刺すのがなかなかうまくいかない様子もすごく伝わってきてなんか良いなあと思いましたし、命をいただくことに対しての著者の葛藤など複雑な心境も飾ることなく素直に描かれており、思いがすごく伝わってきます。現役猟師の等身大の感情、初めて獲れた動物と向き合う中で生まれた興奮や罪悪感などの感情は著者でないと紡げない内容だなと思うので非常に興味深かったです。
猟に興味を持つ方、猟師になりたいと思う方が増えるんじゃないかと思えるくらい魅力的で面白いです。猟師になる予定はありませんが、初めてシカが獲れた喜びや著者の生活を垣間見て、なんかこういう生き方も良いなと狩猟や猟師という生き方に興味が湧きました。なかなか獲れなかったイノシシが初めて獲れた時の文章もめちゃめちゃ良いです。是非、読んでみて下さい。
狩猟の世界にどっぷり浸かろう!想像以上に奥が深いワナ猟の世界をイラストや図解も交えて超わかりやすく解説、ワナ猟のバイブル的な本になるかも!

皆さんはワナ猟についてどのような印象を持っていますか?私は最初は置いておけば自然と野生動物がワナにかかるのだろうとなめた考えを持っていました笑。しかし、実際は勿論違います。本作を読んでワナを仕掛けるまでの状況把握や動物の行動を想像することの難しさや頭脳戦にも似た工夫があることを知りワナ猟の奥深さのようなものを強く感じました。ワナの仕組みが図解で示されていたり、ワナ猟の時の工夫や難しさが丁寧に解説されています。
特に興味深かったのは野生動物が気にする「におい」対策についてです。警戒心の強い動物にいかにワナや人間の存在を気にさせないかの工夫や考えが非常に興味深かったので引用して紹介します。
ワナ猟では、”いかにワナの存在に気づかせず、普段通りけもの道を歩かせるか”ということが重要です。そのため、新しいワナはそのにおいを最大限消し去ることが必要になります。新しい鉄や塩ビでできたワナのにおいは山の動物にとっては異臭そのものでしょう。特にイノシシは、視力はあまりよくないですが、嗅覚は犬の四~五倍とも言われます。どれだけ用心を重ねても充分ということはありません。
ワナのパーツのなかで一番においがきついのが鋼鉄製のワイヤーです。〔中略〕僕はワナをしかけたその日からイノシシがその道を通らなくなるということを何度も実際に経験しています。間違いなくその場所に残ったにおいや気配を察知し、嫌がっているのです。
僕が使っているワイヤーは直径四ミリの軟性鋼鉄ワイヤーで、工業用油をしみこませていないものです。それを大鍋で、カシやクスノキなどのにおいのきつい樹皮と一緒に十時間以上煮込んでにおいを消すのです。〔中略〕猟師の中には自分がワナをしかける予定の山の土を取ってきて、一ヶ月以上埋めておくという人もいます。
塩ビ管のほうは、樹皮を漬け込んだ液に架設直前まで浸しておきます。しかけを作る際の接着剤も極力無臭のものを選びます。
さらなる”におい”対策
ワナだけでなく、自分のにおいも問題になります。ワナを一カ所に設置する二十分ほどの間に、においがどうしても残ってしまうのです。僕は、ワナをしかける前日は、風呂場で石鹸を使わずに体を念入りに洗うようにしています。僕はタバコは吸いませんが、ワナをしかけるしばらく前から禁煙をする猟師も多いです。ただ、人間のにおいというものはどうしても消せないので、最近では、事前にワナをしかける予定のけもの道を頻繁に見回り、いっそのことその山に自分のにおいを付けてしまおうと考えています。ワナをしかけていない時期から僕のにおいを山のあちこちに付けておくことで、獲物に、このにおいは別に危険なにおいじゃない、と認識させてやろうというわけです。
また、ワナをしかける際、ワイヤーの輪の下に穴を掘るのですが、その際に切れる木の根のにおいなどから獲物が穴に感づくという考え方もあります。そのためなるべく穴を掘らずにすむタイプのワナを考案している人もいます。
千松信也「ぼくは猟師になった」新潮社、77、79,82,83頁
「えっ、ここまでするの?」と驚く点が多く、命を懸けた駆け引きの裏側を知ることができ非常に勉強になりました。他にもワナをしかける場所に関する工夫(肉の量が少ない前脚がピンポイントでワナを踏むように仕向けたり、そうなるように想像し工夫すること)や熟練猟師は野生動物の大きさや行動からどういった動きをしたか分かる話など非常に興味深い内容ばかりでした。狩猟に興味がある方には是非読んでいただきたいです。
そしてさらに本書のスゴいところは肉の処理や解体方法を文章で詳しくわかりやすく書いているだけでなくワナの仕組みを図解したり、肉の解体方法を実際の写真を用いて説明しているところだと思います。文章でも十分よくわかりますが、図や写真があることでククリワナや肉の処理や肉の解体の知識が全くない方でもより理解が深まりますし、ワナ猟、狩猟の世界に深く浸ることができます。猟師になりたいとまでは思っていない方もジビエを食べることが好きな人、ジビエに興味がある人は楽しめる内容だと思いますし、猟師(特にワナ猟師)になりたい、興味がある方にはバイブル的な立ち位置の本になるのではないかと思いました。
猟だけじゃない!現役猟師の生き方から楽しさが伝わってくる。普段の生活で触れる事のない生きた情報、未知の世界に心が躍る!

狩猟に関する内容が興味深いことは勿論ですが、本作を読んで個人的に一番面白かった、読む価値があると感じたのが獲物を捕まえた後の料理や禁猟期の生活、猟以外のお話です。作者が調べたり、工夫したり、試行錯誤しながら見いだした生きた情報が満載です。
特に興味深く、著者の野生動物に対する敬意、猟師としての生活の楽しさを感じたのがシカやイノシシを使って作る保存食についてです。例えば、燻製ではロッカーを燻製機として利用したり、ワナ猟の獲物で最も傷んでいるワナにかかった脚の肉や端切れ肉でも美味しく食べるために工夫して「しぐれ煮」を取り入れていたり、シカ肉がマグロに似ていると言う理由から「シカ肉シーチキン」なるものを作っていたり、イノシシの骨まで利用してスープをとっていたりとめちゃくちゃ楽しんでやっているのが文章から伝わってきます。そして、自分が捕獲した動物の命に責任を持ち、命を無駄にしない精神や工夫を感じることができます。これらはすべて材料や作り方が書かれていて、新米猟師さんやすでに猟師として活動している方にも参考になるかもしれません。
毛皮を自分でなめしてみた話もめちゃくちゃ面白かったです。著者の試行錯誤と執念に似た思いが伝わってきて本当に生きた情報とはこのことだなと思いました。独自性があって読む価値があります。しかも皮のなめし方については写真付きで丁寧に説明されており、「千松さん、自分が数年かけて得た知識と技術をこんなに教えて下さりありがとうございます!」と心の中で高まるのでした。
他にも睾丸の味の感想やイノシシの胆のうが薬になる話、野草の話や千松さんが手作りした薪風呂(しかも、こちらも写真付きで解説笑)など目からうろこの情報が盛りだくさんです。「へぇー、そうなんだ」が止まらなかったです。私達が関わることがないだろうなあと思う情報もあるかもしれませんが、逆にそういった情報を知ることができる一冊、、、本の良さを強く感じました。本当に充実した内容。私は猟師になる予定はありませんが、こういう生き方もいいなぁと少し思いましたし、こちらを読んだら猟師になりたいと言う人出てくるんじゃないかな。それくらい魅力的です。猟師や自然の中での生活に興味がある方は背中を押してくれると思います。是非、読んで猟師の世界にどっぷり浸かってみてください。
2.まとめ
食べることが好きな人間として野生動物がどういう形で獲られているか知っておくべきではないかと思い本書を手に取りましたが、ワナ猟の難しさや動物の習性、調理の工夫、シカの数が増えており問題となっていることなど非常に勉強になりました。
正直本作の魅力は語り尽くしたと思うので、もう書くこともあまりないのですが笑、最後にあとがきから。
毎年猟期になると新しい発見や出来事があるのですが、今期もさっそくありました。十一月の下旬に友人の松倉からイノシシがワナにかかったが、日没が迫っていて銃が使えないという連絡があり、急遽鉄パイプをもって応援に。現場に到着してみると、ハラ抜き七〇キロはありそうな巨大なメスイノシシがかかっています。〔中略〕後ろ脚がワナにかかってしまっており、かなり自由に動き回れています。
さっそくイノシシとの間合いを測り、鉄パイプでどつこうとしますが、なかなかうまくいきません。しかも、イノシシの動ける範囲にシダの藪があり、その中に巧妙に身を隠します。〔中略〕そして、さんざん鉄パイプを振り回し、疲れきった松倉から鉄パイプを受け取り、交代した瞬間でした。イノシシが突進してきたと同時にブチッというワイヤーの切れる音。そのあとは、まるでスローモーションのようにイノシシが迫ってくる映像が見え、その次の瞬間には僕の腕はイノシシの体重を感じていました。しかも、そのイノシシはよっぽど怒っていたのか、普通ならそのまま逃げそうなものなのですが、その後も僕のほうにむき直りさらに威嚇をしてきます。急いで木の陰に隠れました。こうなったらどう考えてもかなうはずはありません。緊迫した空気がながれました。ずいぶんと長い間にらみ合ったような気もしますが、イノシシは、僕を威嚇したあと、あとずさりするように再び藪に戻り身を隠しました。どうやらワナが外れたことに気付いていないようでした。
〔中略〕獲物を取り逃がし落胆する松倉とともにイノシシを遠巻きにして、山を下りました。
無事だったからこんなことを書いていられますが、一歩間違えば病院送りも充分あり得る状況だっただけにあとで色々と反省しました。よくよく考えれば、以前師匠の角田さんに「どつく前にワイヤーを周りの木やらに絡ませるようにして、イノシシの行動範囲をせばめておくんやで」と言われていたことも思い出しました。そんな工夫もせずに、イノシシをどつきにかかったのには、やはり油断や慢心があったようにも思います。
また、今年は獲れたシカのうち一頭が見回りに行った時点で死んでしまっているということもありました。別に毎日の見回りを怠ったわけではないのですが、かかった直後に木に絡まってそのまま倒れてしまったようでした。大急ぎで腹を割きました。内臓はまだ温かかったので、いけると判断し、山から下ろし、家で解体したのですが、やはり血が抜けず、肉はかなり傷んでしまっていました。
改めて考えてみると、ワナを仕掛けた場所の斜度がややきつかったようです。もう数十メートル先にしかけたら斜度もまだマシだったのですが、より獲物がかかりやすそうなポイントを選ぶことを重視してしまい、かかったあとのことが充分に考えられていなかったのです。
〔中略〕七度目の猟期を迎えて思ったのは、やはり猟師というのは非常に原始的なレベルでの動物との対峙であるが故に、自分自身の存在自体が常に問われる行為であるということです。〔中略〕自分が暮らす土地で、他の動物を捕まえ、殺し、その肉を食べ、自分が生きていく。そのすべてに関して自分に責任があるということは、とても大変なことであると同時にとてもありがたいことだと思います。逆説的ですが、自分自身でその命を奪うからこそ、そのひとつひとつの命の大切さもわかるのが猟師だと思います。
千松信也「ぼくは猟師になった」新潮社、228~232頁
まず文章の臨場感がやはり素晴らしいです。反省と試行錯誤を続け猟師としてより成長をしようとする様子、作者にとって猟師とはという問いの答えのような内容、この文章だけでも著者である千松さんの人間性や魅力が伝わるのではないでしょうか。私はそれを感じましたし、野生動物を尊び、猟師という生き方を楽しんでいるそんな魅力的な人が書く文章を皆さんにも読んでほしい、そう思います。
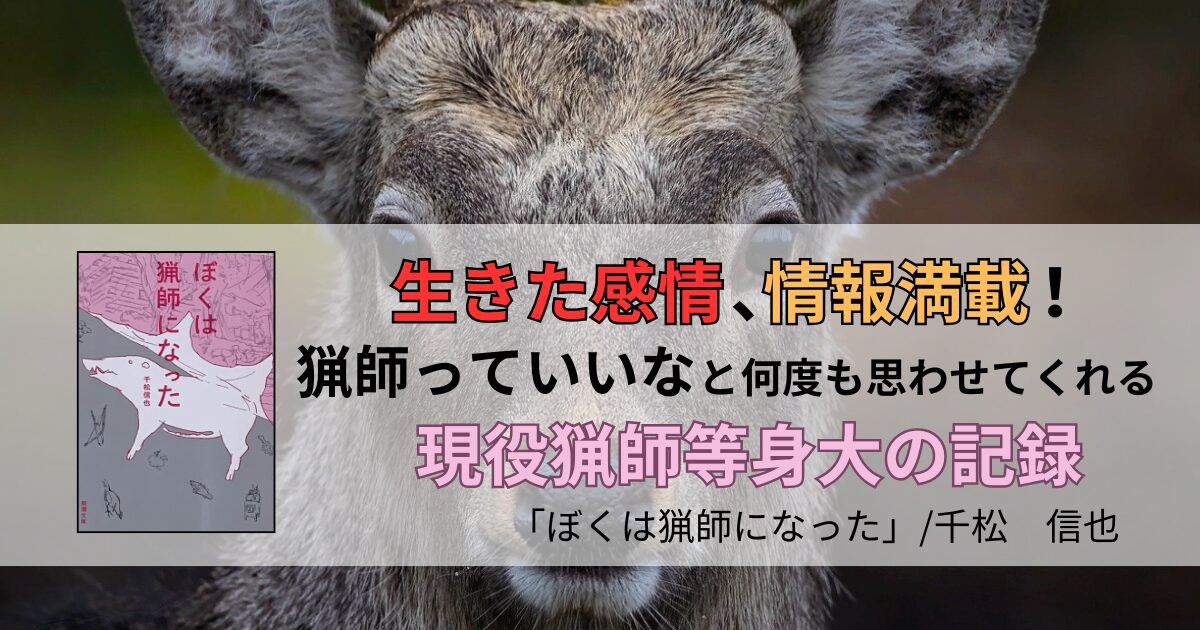
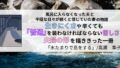

コメント