この度は堀口智之さんの「1杯目のビールが美味しい理由を数学的に証明してみました。」という本を読みました。
内容や構成を簡単に説明すると本作の著者であり、日本初”大人のための”数学塾創業者である堀口智之さんと洋菓子店を営むも経営がうまくいかない数学が苦手なマリさんの2人が日常の何気ない事柄や過去の記憶を数学的切り口で語っていく、会話形式で進んでいきます。(まずこの形式が読みやすいですし、わかりやすいです。)
これは数学に苦手意識がある人に是非読んでほしい。もっと言うと著者は大人に向けて書いているとのことですが、数学が苦手な中学生や高校生にも読んでほしいと思いました。なぜなら、なかなか気づけない数学の面白さに触れる事ができると共に、ものの見方や人間の本質を数学的アプローチから考え、論理的に考えているからです。数学の見方が変わるとは思うのですがこの本を読んで数学が面白い、好きとならなくても、論理的に考えることの重要性や数学を学ぶことが論理的思考を育むことにつながっていることを感じることができると思います。論理的に考え、説明する、そして物事の本質を捉える、この力は社会人では必須の能力だと思いますし、学生さんではそれ以外にも他の科目でも生かすことができると思います。そのため、個人的には読んで損はないなと思っています。
著者の堀口さんは本書のことを「数学を数学っぽくならないよう意識している」、「定義や公式から学ぶのではなく、過去の記憶やエピソードとつなげて数学の世界を知れるように構成した」と語っています。一般的な数学の参考書とは違い定義や公式は出てくるは出てきますが圧倒的に少なく、身近な事柄を数学的観点から考えていくので数字やx、yなどの文字を見て発狂することもなく、入り込みやすいしわかりやすいと思います。さらに本作に登場する「マリさん」が数学が苦手という設定(後半はほんとに苦手かっ??と疑問を持つこともあるのですが笑)なので難しいと思えるところも読者に助け船を出してくれたり補助的に説明してくれるためそちらもいいなと思いました。
数学が日常生活でどのように活用することができるかビジネスや感情に至るまで身近な事柄を用いて書いてくれているので、楽しみながら数学の世界に浸ることができます。本の後半になるほど内容が難しくなる(高校数学の内容になる)ので正直、高校数学でつまずいた私にとっては難しいなと感じましたが、数学がこんな風に日常生活で使われているのかということを知ることができる、数学に興味を持つきっかけになると思います。
私は数学が大好きとは言えませんし、どちらかと言えば苦手です。中学卒業までは数学や計算は得意な方でしたが、高校数学でつまずきその面白さは全く分からず、何を言っているのか全く分からない、助けてくれぇという感じでした。理系の大学を受験したのですが、数学が足を引っ張りまくって直前で国語の受験に変えたくらいです💦そんな数学に苦手意識を持ち、面白さや生活との関わりについて何もわからない自分がタイトルの文言に惹かれ買って読んでみたのですが、結果面白かったです。
もう私は30歳ですが、自分自身が学生時代にこの本に出会えていたら、もう少し数学を見る目が変わったかも、問題を解くためのツールとしてだけでない数学の面白さや奥深さを少し知ることができたかもと感じています。4歳の娘がいるのですが、彼女が数学を学ぶようになったらこの本をあげたいと強く思っています。
それとビジネスマン、ビジネスがあまりうまくいっていない人も読んでほしい!本書を読むと数学が様々なビジネスシーンで応用することができることが分かりますし、論理的に本質を掴むための思考ツールとして数学が重要であることを学ぶことができるのでより生産性を上げたり、未来を予測したりできるかも!?
とにかくめちゃくちゃ面白くて勉強している感じじゃないのに勉強になる本、最高でした。それでは詳しく魅力を紹介していきたいと思います。
~作品情報~
題名:「1杯目のビールが美味しい理由を数学的に証明してみました。」
著者:堀口智之
出版:幻冬舎
ページ数:270ページ
目次
- 数学が「役に立たない」「面白くない」なんてもう言えない!?身近な事柄を例に数学の面白さに迫る大人が早く出会いたかった今までにない数学の本
- 私が読んだ動機
- こんな人にオススメ
- 作品説明
- 数学が生活と密接に結びついていることをわかりやすく解説!堀口先生の数学的切り口で語られる身近な事柄が超面白い!
- 数学を通して生き方や学びのヒント、人間の本質にまで迫る…説得力ある言葉に多くの学びがある一冊
- まとめ
1.数学が「役に立たない」「面白くない」なんてもう言えない!?身近な事柄を例に数学の面白さに迫る大人が早く出会いたかった今までにない数学の本
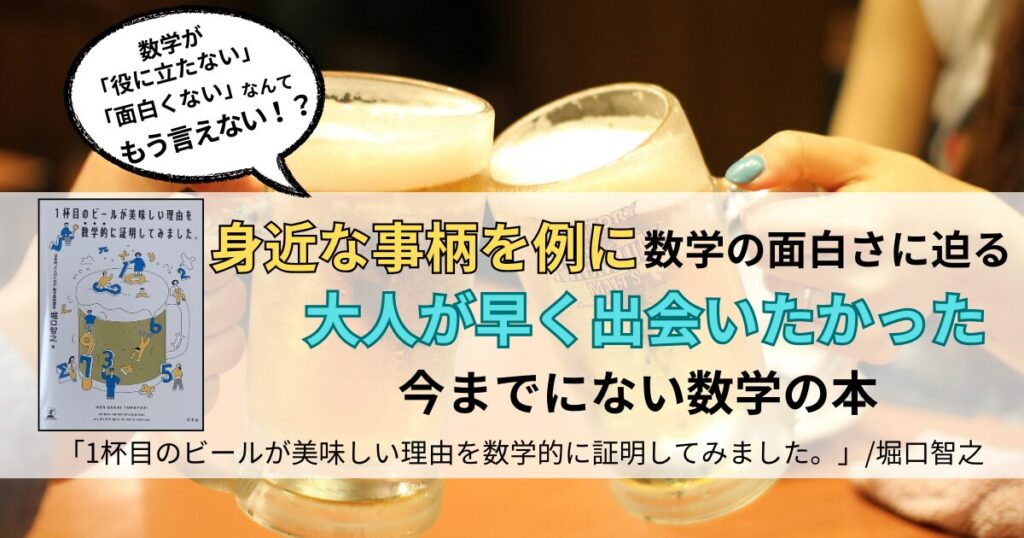
私が読んだ動機
- 私自身高校数学でつまずいた一人で数学の面白さが全く分からない人間だった。だからこそ、数学の面白さに触れたい、どういった形で生活に関わっているか知りたいと思ったから。
- タイトルや帯に書いてあるテーマを読んで面白そうだと思ったから。
- 「ものの見方が劇的に変わる」という文言に惹かれたから。
こんな人にオススメ
- 学生の時に数学の学習に挫折した経験がある人
- 数学がどのような点で生活や社会の役に立っているかあまり分からない人
- 数学はつまらないと感じている人
- ビジネスがあまりうまくいっていない人
- 論理的に考える力、説明する力の必要性を感じている人、身につけたいと思っている人
- 数学を通してより面白い世界を観たい人
作品説明
日本で初めて大人専門の数学教室を創業し、14年間数学を教えてきた堀口智之さんの大人に向けて書かれた数学の本。
洋菓子店を営むも経営がうまくいかない数学が苦手なマリさんと堀口智之さんとの会話形式で語られていくスタイルで定義や公式から学ぶのではなく、過去の記憶やエピソードとつなげて数学の世界を知ることができる。
数学を利用して将来の売り上げを予測したり、1杯目のビールが美味しい理由を明かしたり、「美味しいなら売れる」のウソを論理で見抜いたり……「数学なんて役に立たない」をひっくり返す、大人の教養としての数学講座。
数学が生活と密接に結びついていることをわかりやすく解説!堀口先生の数学的切り口で語られる身近な事柄が超面白い!

「数学をなんで学ぶのか分からない」、「数学は答えを出すもの、受験に必要だから勉強している」、「数学が世界で何かの役には立っているんだろうけど何の役に立っているのか分からない」そんな風に思っている人多いんではないでしょうか。かく言う自分もそうでした。そんなあなたに読んでほしい。そんな思いを全部ひっくり返してくれる面白さが詰まっているので。
例えば、素数。1とその数以外で割ることのできない数のことですが、実はこれは暗号として利用されているそうです。そして面白いのは素数自体は昔から研究されていたそうですが、数学者の間でもほぼ役に立たないと思われており、暗号など必要だと思われて突如脚光を浴びたところです。数学の全てが役立つと思われていないところやそんな中でも素数のようなものを研究対象として面白いと感じて研究している人がいることが面白いなあと個人的に感じました。
他にも価格を決めるとき、新価格でのテスト販売をしなくてもどのくらいの金額で売れるかが2次関数のグラフから予測できたり、等比数列を利用して将来の売り上げを予測したり、微分で将来を予測できたりなどなど、、、。こんなにも数学が身近なもので利用されており、利用する事で効率的に行動することができたり予測を立てることができる。そんな数学の奥深さをただ紹介するとともに、言語化してひとつずつ丁寧にわかりやすく解説している点が素晴らしかったです。
高校数学でつまずいた私は第8章くらいから結構難しく感じてついていけず、眠りに近づいてしまったのが正直な感想です。ただ、数学がどう生活の中で役に立つのかをわかりやすく説明するだけでなく、事柄を様々な角度から見る面白さや重要性を感じることができ、100%理解できなくてもそういったエッセンスを得ることができるだけでも読む価値があるのではないかと思います。
『言葉は全部「不等式」でできていた?』というサブテーマから引き込まれた第4章の内容や考え方が個人的にめちゃくちゃ面白かったので紹介させていただきます。
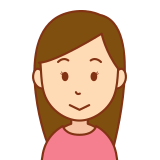
こんな風に現実に不等式が使われているとは思いませんでした。
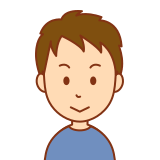
不等式って楽しいですよね。あと「因数分解」なんかも現実での適用を考えるととても面白い分野の一つとなります。
有名なのは、北野武さんの映画作りでの事例です。ax+bx+cx+dxというシーンをx(a+b+c+d)という撮影をしているんです。
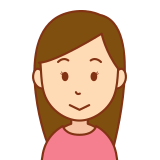
なんかとても面白そうなのですが、全くわかっていません(笑)。
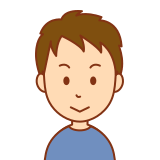
〔前略〕例えば、あるシーンの撮影で、Xさんが、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人をそれぞれ殺害したとします。Aさん、Bさん、Cさん、Dさんをそれぞれ、撃っていくシーンを撮るのは、たしかに事実ではありますけど、ナンセンスであるという風に見えるわけです。
つまり、まずAさんのところにいって銃を撃つ、と。そしたら、Xさんが歩いて行くシーンを映しながら、Bさん、Cさん、Dさんが倒れている姿を映せば、Xさんがやったというのがわかる、という論理です。
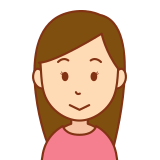
たしかに、映像が見えてくるようです。武さん、すごいですね。
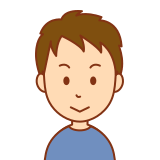
はい、私も衝撃を受けました。もちろん、これは私の解釈ではありますが。でも、こういった因数分解の考え方っていろいろと応用ができるんです。〔後略〕
堀口智之「1杯目のビールが美味しい理由を数学的に証明してみました。」幻冬舎、84,85頁
映画のワンシーンを因数分解として考えるという考え方、捉え方が非常に面白いなあと感じました。因数分解が業務効率化や自動化につながっていることをこのように面白い切り口でわかりやすく解説してくれています。このように捉え方を変えると数学の世界は広がっていくんだろうなと感じましたし、面白くなっていくのかなと思いました。日常生活で自分たちが学んだ数学のエッセンスがどこかにないか探してみると面白いかもしれませんね。
数学を通して生き方や学びのヒント、人間の本質にまで迫る…説得力ある言葉に多くの学びがある一冊

数学は様々なシーンで活用されていること、数学を使うことで未来を予測したり、感情を表現することができることなど「数学は役に立たない」という考えをひっくり返してくれるめちゃくちゃ面白い本なのですが、それと同じくらい面白くて学びになったのが著者が語る生き方や学びのヒント、人間の本質に迫る内容です。読んでみたけど内容が難しかったという人でも先生の言葉から学ぶことは多いと思います。
一番儲かる価格を二次関数から考える第3章の内容を紹介させていただきます。
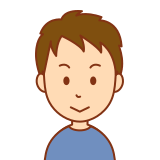
〔中略〕数学の威力、感じていただけました?
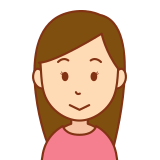
はい、2次関数なんて、なんで学ぶのか全くしっくりきていませんでした。というか、これまでの私の30年間の人生の中で、一度も使ったことはありませんでした。数学なんて役に立たない。そう信じ込んでいました。しかし、今新商品の開発をやろうとしている中で、価格決めに役立つとは……。数学ってビジネスパーソンにとってこんなにも魅力あふれる学問だったんですね。
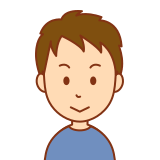
お、気づいてくれましたか?ただ一つ注意点があります。「これは本当か?」という視点です。
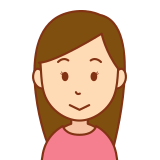
どういうことですか?
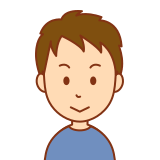
これは本当かと考えてみると、たまたまアンケートで購買者が決まって、たまたま関数が出てきてそれを表現しているに過ぎないので、この値はブレることを前提にとらえなければいけません。
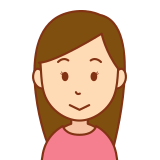
たしかにたまたま、って可能性はありそうです。
〔中略〕
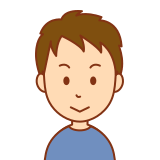
そう、あくまで理論値だと考えて向き合うことが大切です。数学を現実で使うことを考えるなら、「数学に使われない」ことを考えなければいけません。
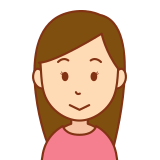
数学に使われない?面白いキーワードが出てきました。
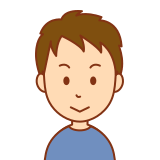
数学を使おうとするあまり、数学だけを信じ込んで数式をいじくりまわしてしまって、正しさを追求してしまうことはよくありますが、現実は時間の経過とともに変化するんですよね。数式を作っている間に現実の数字が変わってしまうこともあります。悲しい結果にならないように、数学に使われるのではなく、数学の支配者になる気持ちで、数学を使いこなしてもらいたいと思います。
堀口智之「1杯目のビールが美味しい理由を数学的に証明してみました。」幻冬舎、71、72、73頁
数学に深く関わっている人が言う言葉だからより説得力がありますよね。他にも数学学習でつまずいた大人への学習アドバイスやボリュームディスカウントの仕組みの回では世の中の心理や裏側とも取れるお話だったり、人が損切りできない理由を数学的に説明してくれたり、、、数学に関する学びと同じくらい刺激や学びが多くありました。面白かったです。気になる方はぜひ読んでみて下さい。
2.まとめ
本書は「大人の教養としての数学講座」というのをメインテーマに掲げていますが、身近な内容を数学的観点から考えていく過程を読めば読むほど「論理的に考える力を育む講座」という裏テーマがあると勝手に感じました。
私自身、数学は計算して回答するために使うもの、受験のためにやっている程度でした。そのような考えの方は少なくないでしょう。しかし、本書を読んでからは数学への見方が少し変わりました。こんなにも数学が生活の役に立っているんだということを知り、そしてその副産物のような形で論理的に考えること、数学的切り口で物事を見ることの楽しさを感じている自分がいました。数学を学ぶってただ計算をする、日常生活で直接的に利用するだけでなく、論理的に考える、本質を捉えるための力になるんだと気づくことができました。
きっと読む人によっては難しい所、興味がない所もあるかもしれませんし、読むのを挫折してしまう方もいるかもしれません(私自身、後半は内容についていくことができず流して読んでしまいました)。でも、論理的に考えることの訓練なんだと思うと数学を学ぶことの意義が見いだせると思いますし、数学の面白さはもちろんのこと、学ぶことの楽しさ伝えてくれている一冊だと感じました。我が子が数学を学ぶようになったら、本書を読ませたい、「論理的に学ぶ練習」をしているんだよって伝えたいなと感じました。
数学に苦手意識がある大人にも子供にも、ビジネスパーソンにもぜひ読んでいただきたいと思います。
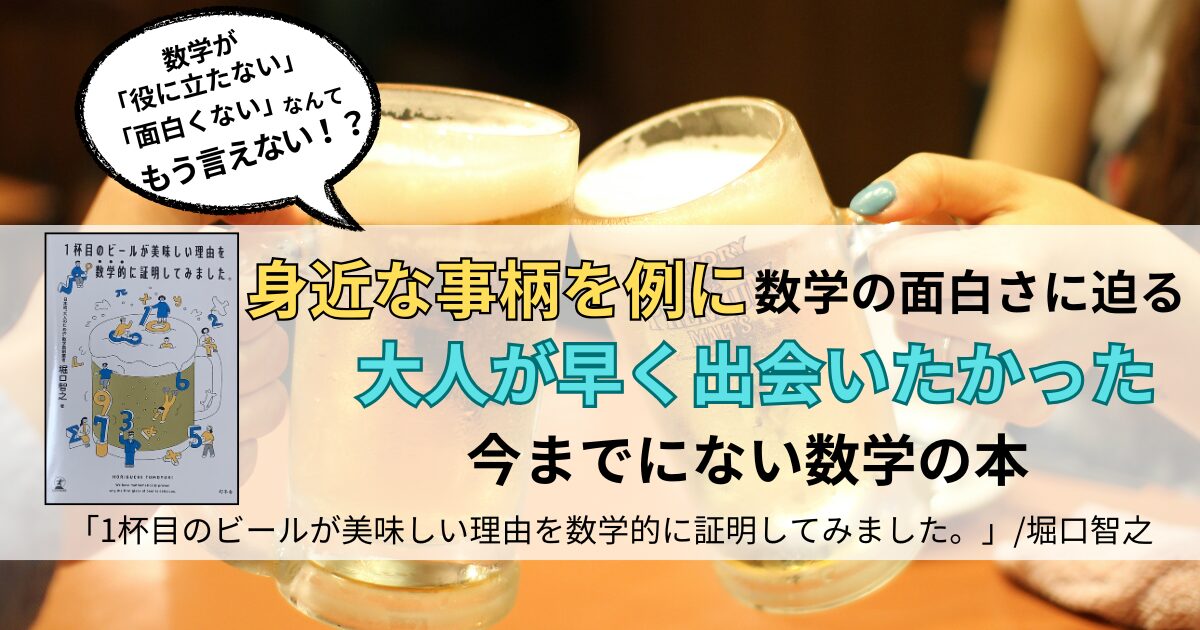


コメント