この度は高瀬隼子さんの「水たまりで息をする」という小説を読みました。
ある出来事をきっかけに風呂に入らなくなった夫とこれからの人生は夫との平穏な日々が続くはずと疑いもしなかった妻、衣津美の物語で衣津美を中心に描かれていきます。
夫婦の形、現代社会の生きにくさや辛くても持ちこたえてしまう人の強さともとれる弱さであったり多くの事を考えさせてくれて考えることができる作品です。
本作のキーワードの一つは「普通」だと私は考えます。最初は水道水を嫌い、ミネラルウォーターで体を流していた夫はいつしか雨を浴びるようになり、最終的に川に行き着きます。そんな風に次第に狂っていく夫は「普通」ではないとは思いますが、では「普通」ってなんだろう?という疑問が本作を読んで湧きました。自分の判断で「この人は弱い人間だ」、「この人は強いから大丈夫」など決めるのは危ういなというのと、「普通」そうに見える人こそそういった危うさをはらんでいるのではないかとそんなことも感じました。それとともに苦しくても「普通」にみせなければ生きていけない苦しさだったり難しさをより強く感じました。
こういったことを感じることができたのは本作が現代に生きる人の息苦しさや精神的、肉体的に辛くても持ちこたえる事ができない人を許せない感情など、そういった心の内部にきちんと真っ正面から向き合って丁寧に描いている作品だからだと思います。現代社会で生きていて生きにくさを感じている人、苦しくても苦しいと言えない人、、、など多くの人に刺さる一冊ではないかと感じました。
また、狂っていく夫と過ごす衣津美の心情の変化も繊細に描かれていて素晴らしかったです。夫の行動や心情が許容できなくなっていく様子や心うちは子供の頃の回想や台風ちゃんという衣津美が幼少期に飼っていた魚も通して描かれていきます。愛しているけれど狂っていく夫を許せないと思う気持ちなど複雑な心境と夫との間に生じる亀裂などを丁寧に描いており、非常に読み応えがありました。
物語のラストは賛否両論あるかもしれません。ですが、精神的、肉体的にきつくても無理をして持ちこたえてしまう人、そんな生き方に息苦しさを感じている人には特に読んでほしいと思いました。もしかしたらこの物語に救われるかもしれません。私は少し気持ちを整理することができました。
それでは本作の魅力を詳しく解説していきたいと思います。
~作品情報~
題名:「水たまりで息をする」
著者:高瀬隼子
出版:集英社
ページ数:165ページ
目次
- 風呂に入らなくなった夫と平穏な日々が続くと信じていた妻の物語―生きにくさや辛くても「普通」を装わなければならない苦しさ、夫婦の形を描ききった一冊
- 私が読んだ動機
- こんな人にオススメ
- 作品説明
- 風呂に入らなくなった夫に寄り添おうとするが……狂っていく夫を許容できなくなっていく妻、衣津美の心情の変化を丁寧に描く。夫婦について考えるきっかけになるかも
- 「辛くても持ちこたえてしまう私達」普通を装って生きていかなければならない苦しさ、強さともとれる弱さを鋭利に切り取った作品
- 残酷さをはらむ衝撃のラスト!生きにくさを感じている人にぜひ読んでほしい一冊
- まとめ
1.風呂に入らなくなった夫と平穏な日々が続くと信じていた妻の物語―生きにくさや辛くても「普通」を装わなければならない苦しさ、夫婦の形を描ききった一冊
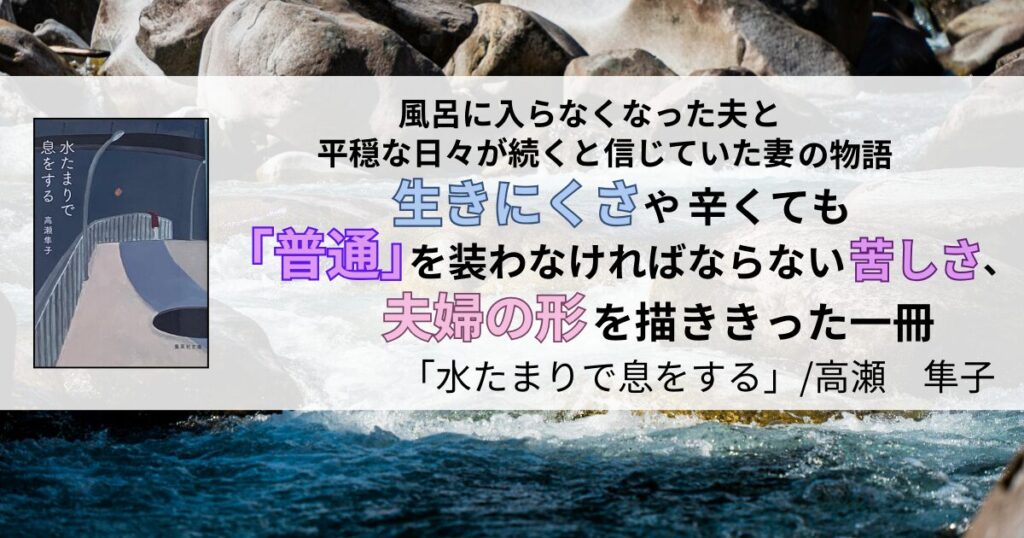
私が読んだ動機
帯の「ある日、夫が風呂に入らなくなった」という言葉や背表紙で紹介されているあらすじを読んで興味が湧いたから
こんな人にオススメ
- 今の社会に生きづらさを感じている人
- 精神的、肉体的にきつくても無理をして持ちこたえてしまう人
- 辛くても辛いと言えない人
作品説明
35歳の衣津実は一つ年下の夫と2人で暮らす。ある日、ある出来事をきっかけに夫が「風呂には入らない」と告げた。問うと、水が臭くて体につくと痒くなるという。何日経っても風呂に入らない彼は、ペットボトルの水で体を濯ぐことも拒み、やがて雨が降るたび外に出て雨に打たれに行くようになる。結婚して10年、この先も穏やかな生活が続くと思っていた衣津実は、夫と自分を隔てる亀裂に気づき――。
今もっとも注目される芥川賞作家が現代社会と家族がはらむ問題を鋭利に描ききった作品。
風呂に入らなくなった夫に寄り添おうとするが……狂っていく夫を許容できなくなっていく妻、衣津美の心情の変化を丁寧に描く。夫婦について考えるきっかけになるかも

本作はある出来事から風呂に入らなくなった夫といつまでも穏やかな生活が続くと信じていた妻を中心に描かれる物語ですが、見出しが「風呂」→「雨」→「川」と変わっていく中で夫の行動、狂い具合もエスカレートしていきます。
最初はなんとか夫の行動を否定しないよう見守り寄り添おうとする衣津美ですが、行動がエスカレートするにつれて次第に夫の行動や感情についていけなくなる変化が繊細に丁寧に描かれているのが魅力の1つだと感じます。2人の間に亀裂が入っていく様は非常に心苦しくなりました。そんな衣津美の感情の変化を丁寧に描いている点が素晴らしいと感じます。引用させていただき、一部紹介させていただきます。まずは風呂に入れなくなった最初の頃のシーンです。
「え、どうしたの。もう出たの」
夫は裸のままだった。肩から黒いバスタオルをかけていた。近寄って、タオル越しに夫の肩に手を当てる。タオルはほとんど濡れていなかったし、夫の体も、髪も、見える限りはどこも濡れていなかった。
「無理だった」
と夫は言った。目の下がしわしわだった。
「だめだった。シャワー、浴びれなかった。なんだかもう、嫌で」
彼女は夫の肩から背中へ手を当ててなでた。上から下へ繰り返し手を動かし、腰の手前で途切れるバスタオルのぎりぎりのところで、一番上に手を戻して、また下へとなでた。
水がくさいんだよ。それで、それが体に付くと、かゆい感じがする。〔中略〕これまでどうして平気でこんなものに触れていたんだか分からない。こんなくさいものを飲んだり、体にかけていたりしていたなんて、思い出すと、それも嫌になる。ごめん。
裸のまま話をした最後に、夫はそう謝って、彼女が差し出した新しい下着とTシャツと短パンを順番に身に着けた。そうした方がいいだろうと思い、Tシャツは色の濃いグレーのものにした。
夫を労り、夫の話に耳を傾けながら、彼女はひとりぼっちで話をしている。もしかしてほんとうに、ずっと風呂に入らないつもりなの。驚いている。このおだやかな人と結婚して、三十代も半ばを過ぎて、自分の人生には、この先想定していない出来事なんてもう何も起こらない気がしていた。子供を産むのは止めたし、夫婦二人でそれなりに楽しく、年老いていくのだろうと思っていた。年老いて、と想像の中では時間の歩みが速く、飛び石のようだった。三十五歳の今、五十歳くらい、七十歳くらい、そして死。
夫は冷蔵庫から新しい缶ビールを取り出して飲み始めた。彼女はもうビールは飲みたくなかったけれど、喉が渇いていて、けれど今夫の目の前で水道水を飲むのははばかられ、仕方なく同じ缶ビールを取り出して飲んだ。洗面台の床に残されたペットボトルの中には、夫が顔を拭くのに使ったミネラルウォーターがまだ余っているはずだけれど、それこそ飲めるわけがなかった。
高瀬隼子「水たまりで息をする」集英社、19,20,21頁
夫の肩から背中へ手を当ててなでる、夫を労り夫の話に耳を傾けるという優しさにあふれる行動と共に、Tシャツを色の濃いものにしたり、水道水を嫌う夫を気遣い、水ではなく飲みたくないビールを飲んだり、、、そういった配慮や思いやりの心に優しさや愛情を感じました。直接的な優しい言葉よりも優しさを感じる行動をいくつか描くことで風呂に入らない夫に戸惑いながらも寄り添おうとする妻衣津美の心の内がより強く感じることができ素晴らしいと感じました。
小説の最初はこんな愛を感じる文章ですが、夫の行動を許容できなくなっていく様や葛藤など衣津美の心情の変化がしだいに描かれ、そういった心境を時にストレートに時に比喩なども用いて丁寧に描いています。そちらも紹介させていただきます。夫が会社を辞めたことを衣津美に報告する場面です。
夫と二人でスーパーに買い物に行くと、周りの人がさりげなく夫と距離を取るのが分かった。東京の人たちはくさい人にわざわざくさいと言ったりしない。じろじろ見ることもしない。ただ「やばい」と気づくと、すっと流れるように離れて行く。スーパーでもそんな風だから、当然、通勤電車や会社でも周りから距離を取られているだろう。夫がそんな視線や他人の態度に傷ついていないはずがなく、そんな状態で働き続けられるわけがないのに、彼女は夫が仕事を辞めたことが信じられなかった。決めてしまったのだ、と思った。
〔中略〕「失業保険ももらえるだろうし、貯金もけっこうあるし、しばらくゆっくりしても大丈夫じゃないの」
しばらく、という曖昧な言葉で濁していると、自分でも分かった。
彼女の収入だけで生活していくことはできる。逆の立場だったら、夫は彼女を養ってくれただろう。けれどそうなった時、彼女は夫の負担になるだけの自分が許せないだろう。一人で田舎に帰っただろう。そして一人で田舎に帰るのがどうしても嫌だからこそ、なんとしてでも、バスタブをペットボトルのミネラルウォーターで満たすために、働き続けただろう。風呂に入らなくたって、それで、職場の人に嫌な目で見られたって。今だって良い目で見られているわけでもないんだから、別に。
そんな風に無理やりに自分に置き換えて考え、「わたしだったら我慢した」と、そんなのは自分を追い詰めるだけの無意味な思考遊びに過ぎないと考えたそばから否定もできるのに、そうして考えて、ようやく、わたしは夫に怒っているのだ、と気付く。夫の弱さが許せないのだ。
全部損なって、ぼろぼろになってほしい。
二人の生活をこのまま継続させるために、自分を殺して生きていってほしい。
違う。そんなことは思っていない。そんなわけがない。
夫には、健やかに幸福でいてほしいと思っている。ほんとうに、二人でいつまでも仲良く、平和に生きていきたい。数年間の治療を経ても子供ができなかった時、これ以上はもういい、と自然に思った。時間とお金をかければもっとできることはあったけれど、それに投じる様々なパワーがなかった。元々あったものが尽きたというよりは、元々空っぽだったところに、外から燃料をそそいでいたけれど、そのそそぐのにだって力がいると気付いて、もう止めればいいと思ったのだった。
二人きりの人生を遠くまで想像できた。何歳になっても、自分たちは平和で穏やかな暮らしができると思っていた。満ち足りているわけではない、代わりに、決定的な足りないものだってなかったはずだ。衣津美は、夫が人生の全てとは思わない。けれど、夫がいてくれたらそれでいい、とは思っている。その二つのことは、似ているようで違う。夫にとって自分もそうであったら良かった。
許したくてしんどい。夫が弱いことを許したい。夫が狂うことを許したい。だけど一人にしないでほしい。
高瀬隼子「水たまりで息をする」集英社、113,114,115頁
夫を許したいけど許せない、夫には幸福でいてほしい、二人で平和に暮らしたいと思っているけれど思っているからこそどうにか夫にも社会の中の歯車として生きていてほしいという葛藤が強く伝わってきます。
なんやかんやいっても結局は夫も何とか持ちこたえるだろうと思っていたけれど、現代社会からフェードアウトした。その事実が同じように色々な理不尽や不満のなか「持ちこたえて生きながらえている」衣津美には許せない。その気持ちも本作を読んでいただくとすごくわかるのでなおさら胸がヒリヒリしました。「夫が仕事を辞めてしんどい」、「夫が狂ってしまってしんどい」だったら分かるんですけど、「許したくてしんどい」という言葉にはそれ以上の衣津美の心の苦しさや少しの愛が詰まっているようでやはり心苦しさを感じました。
最初に引用させていただいた文章と比べると明らかに夫への感情の部分で変化が分かると思います。根底には夫と変わらず生活していきたいという気持ちがあるのでしょうが、それでも夫との間に次第に亀裂が入っていく、その段階的な衣津美の心情の変化を丁寧に描いていて非常に読み応えがありました。
「パートナーが風呂に入らない」という現実は私達にも明日訪れるかもしれない出来事なわけでそういう身近に隣り合わせにある一種の恐ろしさを描くことで自分だったらどうするか、問題提起されている感じがしました。夫婦の形や人間関係など考えさせらることが多かったです。丁寧に描かれていく衣津美の心情に触れて家族のかたちについて考えてみませんか。
「辛くても持ちこたえてしまう私達」普通を装って生きていかなければならない苦しさ、強さともとれる弱さを鋭利に切り取った作品

夫は風呂に入らなくなり、いわゆる「普通ではなくなっていく」わけですが、現代社会では「普通」でなければ、「普通」を装わなければ生きていけませんよね。理不尽な上司やクライアントの要求、心ない言葉、劣悪な職場環境などなど、誰も皆何かしらの苦悩を抱えているのではないでしょうか。いつも生きるだけで手いっぱいですよね。それでも皆生きていくため、家族を守るため、時には歯を食いしばって生きている。それは私達だけでなく、本作の登場人物である衣津美も同じです。
本作は人間社会の歯車の一つとして普通でいなければ生きていけない難しさ、何か問題を抱えていたり、普通でなくなろうとしそうになっても「普通」を保って生きていかなければならない苦しさ……そんな多くの人が抱える問題を鋭利に切り取った作品だと思います。そして、持ちこたえてしまう衣津美のそうできなかった夫に対する心情の変化も時に残酷に丁寧に描いている作品だと思います。
特にそれを感じさせるたのが衣津美の子供の頃にあったことを思い出す回想シーンで母が父に義母の介護が辛いことを伝えるシーンでした。引用し紹介させていただきます。
夜中に目が覚めた。まだ小学生の時だったと思う。こわい夢を見た。川と台風ちゃん(※衣津美が子供の時川で拾ってきた魚につけた名前)が出てくる夢だった。そういえば今日台風ちゃんに餌をやったっけ、と餌やりなど普段は母に押しつけて自分では滅多にやらないくせに、妙に気になり出し、もう夜中だけど、ちょっとだけあげよう、と思って布団から抜け出した。じっとりした汗でパジャマが湿っていた。
寝室に両親の姿はなく、彼女は起き上がって部屋を出た。実家は二階建ての一軒家で、寝室は二階に、リビングは一階にあった。階段を半分まで下りたところで、リビングで話をしている両親の声が聞こえた。母が「お義母さんのことだけど、もう、つらい」と言った。彼女は階段の途中で立ち止まり、息を殺して耳を澄ませた。それは確かに母の声だったけれど、彼女には向けられたことのない厳しさをにじませていた。それに応える父の声も聞こえた。
「ほんとうにつらかったら、病気になるだろう。おまえは大丈夫だよ。がんばってるじゃないか」
〔中略〕父は、母を励ますように、職場にいるうつ病になった同僚が、うつ病になる前どれほど大変な仕事を任されていたか、家族に悲惨な不幸があったか、長い時間をかけてたくさんの事例を挙げ説明した。
「津夕子は、」
その時、父が母を「ママ」ではなく名前で呼ぶのを初めて聞いた。
「津夕子は、病気になるような弱い人間とはできが違う。さすがおれの見込んだ女だよ」
衣津美は、そういうものなのかと思った。賢い父の言うことだし、母を励ましていて優しいし、母も「がんばる」と応えていたから。世の中には病気になるほどしんどいことがある人だっていて、だけど、お母さんはまだ病気になっていないから大丈夫なんだ。
その話を階段で聞いてしまったことは、両親にばれてはいけないような気がした。彼女は足音を殺して階段を上がった。〔中略〕空気が鼻を通って体に入って行く音を、いつもより大きく感じた。寝室に戻りタオルケットにくるまりながら父と母が話していたのは大人の世界の話だと思った。だから自分は、大人になるまで、きっとこのことを覚えているだろう。
高瀬隼子「水たまりで息をする」集英社、60~62頁
「津夕子は、病気になるような弱い人間とはできが違う。さすがおれの見込んだ女だよ」
「病気になる人間=弱い人間」「病気にならない=大丈夫」なんだろうか?きっとそんなことはないはずだ、、、
うつ病になった同僚はそうであってもお母さんの苦しみとは直接的な関わりはないよな?お母さんの苦しみはお母さんの苦しみとしてきちんと向かい合ってあげてほしい、、、
沢山考えさせられることと感じることがある文章だと思います。
苦しくても持ちこたえて何事もないように見せかけてしまえる人が「メンタルが強い人」、「パワフルで強い人」なんて言われる風潮があって、そういった人が評価される社会ではあるなあと感じるのですが、実際はどうなんでしょうか。たしかにそれは「弱くない」ことではあるかもしれないけれど、辛くても持ちこたえて頑張ることは「強い」ことになるのでしょうか。逆に「つらい」と言えないことは「強さ」ともとれる「弱さ」ではないでしょうか。
私自身色々なことを考えさせられましたし、きっと読んでいただけると著者が現代社会の生きにくさ、都内の人の人への関心の無さ、田舎での人への過干渉なども鋭利に描いている作品だと感じていただけると思います。そして、人それぞれ考えること、感じることが多くあるはずです。
是非読んでみて下さい。
残酷さをはらむ衝撃のラスト!生きにくさを感じている人にぜひ読んでほしい一冊

風呂に入らなくなった夫とずっと続くと信じていた平穏な日々が壊れた妻が行き着く先はどこなのか。
読み進めていくと結末が気になっていくと思いますが、少し残酷さをはらんだラストが待っています。
ネタバレにになるため詳しく書くことは避けますが、今まで読んだ中で1,2を争う衝撃の展開でした。最後の7ページは非常に残酷さをはらんだ内容でこんなに胸が苦しくなる最終ページはあまりなかったです。賛否両論あるかもしれません。
希望も何もないかというとそうではないと思っています。きっと皆が喜ぶラストではないけれど、それでも個人的には「普通」に生きていくことの息苦しさや人間の正直な気持ちだったり痛みをきちんと描ききって下さっていて、その痛みに、苦しさにきちんと向き合っている本作は似た感情を持つ人を救う一助になるかもしれないと思いました。
きれい事で終わらせずきちんと物語や登場人物に正面から向き合った著者の執念のようなものを感じました。物語の結末はご自身の目で確かめてみて下さい。
2.まとめ
変に良いように終わらせない、甘くない現実を突きつけてくるのがこの小説の良いところだと感じます。「普通」でいられない、「普通」でいられなくなった人をどうしても許せない気持ちや心ない言葉をかけてくる人達とどう関わっていくべきかなどそういった問題に真っ正面から切り込んでおり、多くことを考えるきっかけをくれる一冊だと思います。
私自身も自分よりも仕事ができないと思う人には「なんでこんなに仕事ができないんだろう」とか何か悩んでいる人を見るとそんなに悩まなくても良いのに、、と思ってしまうこともあります。しかし、本作を読んで弱さを許容できない自分を再認識し、問題意識を持つことができました。辛くても、持ちこたえてしまう、普通に見せてしまう、強さとも言える弱さに気づける人間になりたい、少しでも人に優しくなるべきなのでは?寛容な心で受け入れるべきではないか?と感じました。また、弱さがあってもその人の強さに目を向けていきたいと思いました。
また、本作を読んで想像以上に自分が辛くても人は気付いてくれないだろう、人はそんなに他人に興味をもっていないのだろうとも感じました。どちらかというと私も肉体的、精神的に辛くても辛いと家庭でも職場でも友達でも言えなくて持ちこたえてしまうタイプではあるかと思いますが、これからは辛いときには助けを求められる人間になりたい、実際は難しいことの方が多いと思いますがもうダメだと思えば現実から逃げるのも一つの手かもしれない、そんな風にもこの小説を読んでからは考えています。
このように社会が抱える問題点など描いている本作によって自分自身の弱さを見つめ直すことができ、ネガティブな要素に対して前向きに考えることができました。きっと自分の弱さを感じている人、生きにくさを感じている人にこそ刺さる小説だと思います。
台風ちゃんという衣津美が幼少期に家に持って帰ってきて世話をしていた魚が衣津美や夫とも重なる部分があり、そちらについても言及したかったのですが、長くなるのと物語に大きく関わる部分だったため扱うことができませんでした。台風ちゃんという存在を通して物語を見ることで現代社会や人が抱える問題をより強く感じることができると思います。
是非読んでみて下さい。
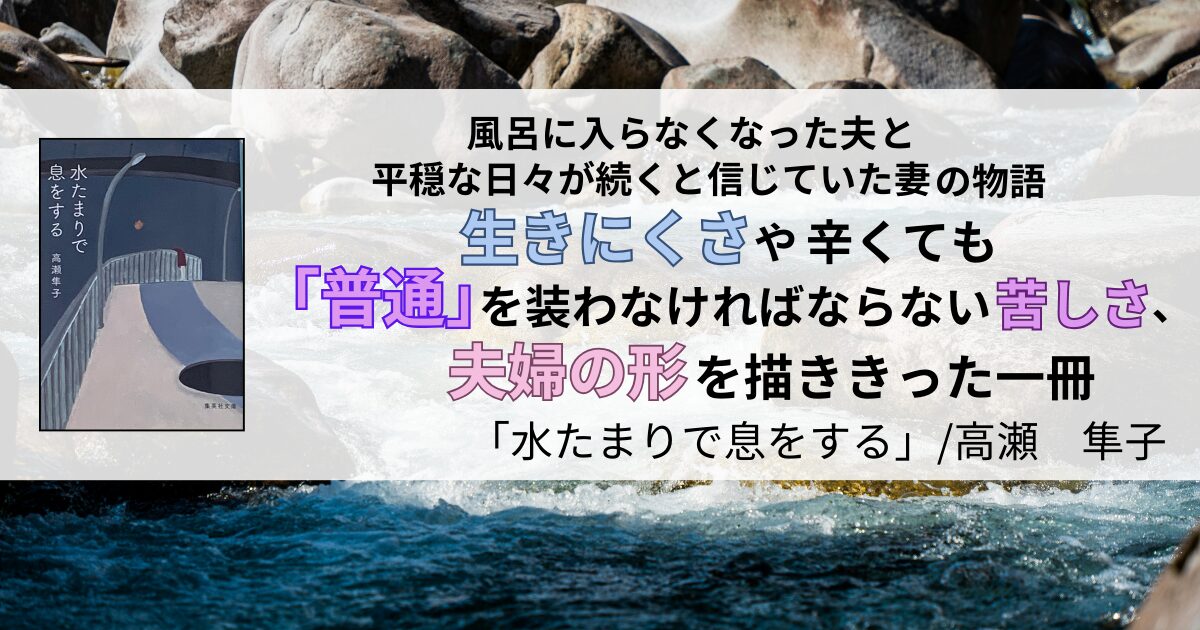
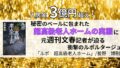

コメント